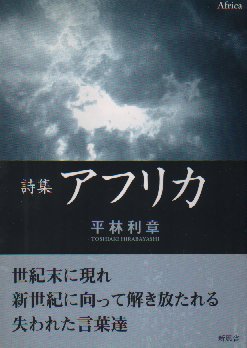
詩集アフリカ 前半部
ISBN4−7974−1289−5 C0092
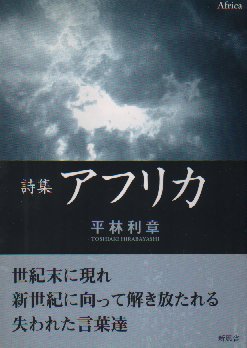
まぼろし
埠頭を横切り
一人海岸に立っていると
遠く死の島が見えるようです
そこは今の私にとって
憧れであり
恐怖でもあるところ
そこから誰か手を振っているよう・・・・・・
おもわず歩み出すと
海水の冷たさが私を我に返します
やがて海水が靴に染み込んで
いつまでも いつまでも
乾かないでいると
波が私をさらうように
押しよせては 引いてゆき
砂に染みて私を置いていきます
新世界
家出の最終手段。トラックの荷台に忍び込み、街を出る。夜には風が冷たく、光や闇さえ、希望と恐怖を自覚させる。
朝だ――黎明時――新世界が開かれる。昨日吸った空気とは違う。
大人は最後の航海へ向かうのだろうが、僕は新しい航海に心震わせる。
煙草に火を付け吸ってみる。煙の行方は僕の足取りと一緒だ。
何も知らず海は青く、風は鳥を運んでくる。
荷台からは、身を乗り出し、ずっと海を眺めていた。
すると、急なカーブに差し掛かり、勢いよく荷台から放り出されてしまった・・・・・・。
つかのまの世界だった。
しばらく倒れていたが、上半身だけ起き上がってみる。
突然、恐怖が水平線から湧き上がる。――雷雲だ。
痛みをこらえ、這いつくばり、ガードレールまで辿り着くと、さっき倒れていた場所に、物凄いスピードで真っ赤な車が通り過ぎていった。
僕は、この世の涯で一人ぼっちだ・・・・・・。
雨に濡れ、風に吹かれ、もう行き場もなくうずくまっていると、
新世界が逃げて行くのを感じる。
特異点
僕の魂がコンパスのような足を持ち
宇宙の果てに踏み出すと
そこは
僕が僕でなくなり
星が星でなくなり
闇が闇でなくなり
物質が物質でなくなる
どこにも行き場がなく 追いつめられ
いよいよ宇宙に問うた
人間が生まれた事は「是」か「非」か?
すると宇宙は恥じらうように赤くなり 急に収縮し始めた
僕はその中心に投げ出された
やがてそこは赤い色から黒くなり
もうこれ以上は小さくなれないと震えだし
一気に爆発した
あとはただ 天の川の白く濁った水の中で
ユラユラ ユラユラと 漂っているのだった
アフリカ
私がある貧民街に立ち寄った時のことです。みすぼらしいレストランで食事をとったのです。おかみは黒人で、米のようなものが入った皿を私に出してくれました。それはあまりにもおいしい味がしたので何杯もおかわりをしました。
やがて食事も終り、支払いを済ませていると、奥のほうにうずくまっている娘がいます。おかみは何も言わず怪訝そうに私と一緒に娘を眺めていました。そばに寄ってみると黒人の娘で、なかなか美しい顔立ちをしていました。体を丸め、膝を抱えたその体を抱き起こしてみると、風邪をひいているらしく、ゼェゼェと息を荒くしています。ひどく汚れていたので、医者に連れて行き、治ったら風呂に入らせようと思い、おかみに医者のいる場所を尋ねると、「山の上」とだけ言い残し奥に引きこもってしまいました。
私は車に娘を乗せると山の上にいる医者の所へと車を走らせました。
暫く行くと家屋が見えてきたので水をもらおうと思い立ち寄りました。家の中から人が出て来て水をくれましたが、助手席に寝ている娘に水を飲ませようとしたら、たちまち顔が険しくなり、少し離れた家の人間を呼びに行ったのです。私には理由が解らなかったのですが、恐怖を覚え、再び車を走らせました。
山道をくねくねと曲っていると、バックミラーにチラチラと写るものがあります。車を止めて見てみると、それはさっきの人が数人を従えて私達を追って来るのでした。いったいどうしたというのだろう。私は娘の顔を見ました。娘は頬を赤らめて苦しそうに息をしています。私は早く医者の所に着くようにと祈るように車を走らせました。
*
山医者は山を登りきった所のひらけた土地に家をかまえていました。
私は軽くドアを叩き、出て来た医者に娘を見せました。すると、医者も白い顔を真っ赤にしてなにやら怒鳴りちらすのです。私はなんとなく気づいていたのですが、こんなにひどいものだとは思いませんでした。さっきの人といい、この医者といい、恐怖にも似た怒りの表情をします。それは私の頭に緊張をもたらし勘を働かせたのです。
私はまたも逃げ出しました。しかし、医者も山の人達も、いっしょくたに追いかけてきます。いくらアクセルを踏んで速度をあげようとしても、なかなか速度があがりません。いや、アクセルを踏んでいるのですが、そう思っているだけかもしれません。あいかわらず彼等は追いかけてくるのです。私は逃げている意味も忘れ、ひたすら車を走らせました。どうやら私に原因があるのかもしれません。私はただ、娘を助けたいだけなのに・・・・・・。
車は完全に山を出て街なかを走っていました。
しかし、何もかもが怖くなり、ビルのなかにいる人間、店で果実を売っている人間、通りすがりのこちらを見ている人間、街の人すべてが私達を追いかけてくるものと思い、こらえきれず車を走らせ続けました。
*
どのくらい走り続けたことでしょう。私の目に、はっきりと景色が映りだした時、車は線路の上をゆっくりと渡っていました。向こうに見えるのは海でしょうか? 潮の香りが匂ってきそうです。私は我に返りました。そうだ、娘はどうしただろう。助手席の娘の方を見ると、――あぁ、なんということでしょう。娘はとうに死んでいて、体中に繭の様なものが張ってあり、死臭すら放っているではないですか。そのあとの私はどうしたかまるで覚えていません。彼女は本当に存在したのか、彼女を車ごと海に沈めたのか、さだかではないのです。ただ一つ言える事は、今、私はこうして病院に入っていて、逃げ出しては捕まる毎日を送っているのです。
〜一九八八・夏〜
銀の糸
辿り着くと目の前に川があった。
川面に柳が垂れている。その横で川を覗き込むと、髪が柳のようにしな垂れた。川に反射する光に心が参る。私は苦しくなって、木に手をあてひざまずく。すると、川上から舟がやってきた。舟守が私の目の前に舟を止めると、さあ、乗れ! と促す。
「いやだ、舟なんかに乗りたくない」
「いいから乗れ!」
「いやだ、いやだ」
あぁ、太陽よ、お前もそんな顔をして私を責める。光を射すな、光を。お前の光が金色に歪み、はっきりと物を見えなくする。人よ話すな! 話し声が光となって襲いかかり皮膚を刺す。私の頭の中に入り込み、乱反射して脳をかき乱す。頭が重い。痺れるようだ。いっその事おもいっきり泣けたらどんなにか楽だろう。なぜか涙がでない。
やっとの思いで身を起こすと、舟守がこっちを見ながらにやにやと笑っている。
「お前は何者だ!」
「私は君との出会いを約束された男である」
「私をどうしようとするのだ」
「舟に乗せて川下に向かう」
「川下にずうっと下ったら海に出るではないか」
「そうだ」
「その先はどうなるんだ」
「君を苦しみのない世界へ連れて行ってやる」
「苦しみのない世界?」
「そうだ」
「そんな世界などあるわけがない」
「川の流れとともに君も流されるのだ」
「私は今お前にかまっている暇などないのだ。自分の事は自分で決める。私の前から消え去れ!」
「・・・・・・そうか。残念だが仕方がない。これからどうするのだ?」
「帰るべき場所を探す」
「それならば、君から出ている長い銀色の糸を手繰り寄せ、その先をたどって行けばいい」
「どういうことだ」
「銀の糸。その先をたどれば、君の帰るべき世界に行けるだろう」
「本当だろうな!」
「嘘だと思うなら試してみるがいい。ただし、道中けっして人を横切らせてはいけない。糸が切れてしまうからだ」
「糸の先をたどればいいのだな?」
「そうだ」
「わかった」
なるほど、確かに私の体から糸が出ている。触ってみるとゴムのような感触で意外と丈夫なようだ。私はゆっくりと糸を手繰り寄せ、歩き始めた。
糸は私が通ったであろう街々へ複雑に伸びていた。
しばらく歩くと、人が前の方で横切った。切れる事はないだろうと思ったら、人はかまわず歩き続け、糸がどんどん伸びてゆく。私は急に気持ち悪くなり、必死で人を追った。その人の左前に出て、右前へ横切り、糸を人から振りほどいた。その人は、「なにごとだ」とでもいうような顔をして、怪訝そうに私を見た。この人には見えないのだろうか? 私は糸を振りほどくと、また歩き続けた。
幾日そんな事が続いただろう。私は押し出されるような思いがして引っ張られた。あぁ、糸が、糸が切れる。
すると、私は母親の胎内から飛び出し、生まれて初めて泣いたのだった。
約束の門
それは、ある吟遊詩人が雲の上の見えざる者に大声でこう言われた事から始まる。
約束の門に行け! そこでお前が何者であるか。真実とは、生きる目的とは、何であるのか、全てが解る。道順は、―――。
詩人は歩き始めた。
途中出会った老人に道を尋ねる。
「パルナシオンの山はあそこですか。あれがそうだとすると、目的地に着くのですが」
「あんた仕事はどうしたんだい。こんな所でウロウロしてないで働きな!」
「私にそんな暇はないのです。では、先を急ぐので・・・・・・」
しばらくすると後ろから声が聞こえる。
「おーい、あんた××だろう? あんたの奥さんに子供が生まれたってよ。早く帰ってやんな」
「お前は誰だ? なぜそんな事を知っている?」
すると後ろから来た男は不快な表情をして後ずさり、舌打ちしながら引き返した。
あらゆる方向から声が聞こえ始める。
「お前は嘘つきだ」「やめちまえ」「そんな事をして何になる」「俺の言う事を聞け」「俺は正しいんだ」「お前は常識はずれだ」「やめてくれ」「お前だけそこに行くな」「うらやましい」「くやしい」「その門すら見る事が出来ない」「ちくしょう」「やめろ」「やめろ」・・・・・・。
詩人は邪悪な声を振り払い、歩き続けた。山を見据え、河を渡り、幾千もの丘を越え、何日も歩き続けた・・・・・・。
ようやく、門が見えた所で、両手を広げ走り出す。
「見えた! 見えるんだ! 私には門が見える! とうとう着いたのだ。忌まわしい者どもから遠く離れて・・・・・・」
詩人の足は血にまみれ、手は傷だらけである。
そう、純粋な者だけが血まみれになればいい。
吟遊詩人は今までの疲れが出たのか、門の前まで来ると急にへたりこんでしまった。
すると、門の中央にある、太陽のような、獅子のような像がこの若者に問うた。
「私は約束の門の門番である。お前は何をしに来たのだ」
「わたくしは・・・・・・あぁ・・・・・・」
「お前はあらゆる苦労をしてきたようだが、目的を言わなければこの門を通ることは許されない」
詩人は両手で顔を覆い泣き叫ぶ。
「・・・・・・私は・・・・・・わたくしは・・・・・・忘れてしまった」
開港記念日
夕闇迫る公園をぬけて坂道を上ると、オレンジ色の灯をともした教会が見えてきました。夜にはささやかな夜会が開かれるそうです。
長く続くレンガ道を通り、丘にたどりつくと港が見えるのですが、どれもこれも色とりどりの綺麗な光を放った船が停泊しています。
テラスには小さな白いテーブルに、大きな赤い帽子をかぶった女の子が、音楽にあわせてストローをタクトにビュンビュンと振っています。
丘を越えた所にはふだん人が住んでいない西洋館が建っているのですが、今日ばかりは窓に灯りがともっていました。
館の前のベンチに腰をおろすと、子供達だけの奇妙なパレードが通り過ぎます。
「きっと明日には終ってしまうこのパレードで、今夜一日だけのティンカーベル達は、大人なんか目に入らないのだろう」
風はゆっくりと木々に向かって吹きはじめます。
赤や黄色や青色の旗が風になびき、霧笛の音に振り向くと、煙のたちこめる行列の向こうに白い帽子を被った少女が目に留まりました。
私は愕然としました。
あの頃と何も変らない姿で私の前に現れた初恋の君。驚きのあまり体が動きません。
「まさか・・・・・・少女のままではないか!」
昔とまるで変っていないのです。
「もし、幻ではないとしても、私の事など分かる筈がない。片思いだったのだから」
にわかに音楽が大きく鳴り響き、少女は誰かと話している様なのですが良く聞こえません。
すると突然、少女が私の所に駆け寄って来たのです。そして、なにやら話しかけてきましたが、なにぶん音楽が大きすぎて良く聞こえないのです。
意味もなくただ茫然と首を振っていると、キョトンと大きな目を見開き、しばらく私の顔を不思議そうに見ています。
やがてニッコリと微笑むと、船の方へ駆け出していってしまいました。
「私は思い出を取り戻しにここに来たのだろうか? いや、そんなことはない。彼女は私の事など知っている筈がないのだ!」
私は雨の振り出した港を後にしました。
街角
黄昏てゆく街角に 一人 ビルの間をすり抜ける
風に吹かれている
ビルの窓ガラスに 無数の枯れ葉が 当たっては落ちる
通り過ぎる車のクラクションに 振り向くと
まだ あどけない顔の恋人達が 足早に道路を横切って行く
失くしてしまったものに気づいてしまう
冷たい歩道橋の手すり
「愛している」の落書き
ポケットに手をつっこみ 溜め息ついて
風にコートが持っていかれそうだ
こんな日もあっただろう
子供の差し延べる手に アメ玉ひとつ
ちょっと怯えた瞳
おもわずしゃがみ込むと
急に駆けて行ってしまった
未来だろうか?
いつのまにか一人ぼっちになってしまった僕の目の前を
落ち葉が音も無く舞い上がる
触発
まだ 街が目覚めていない頃に 君は生まれ
人の目をまともに見れず 石を二つ置き
君は駆けて行ってしまった
石は時間が経つにつれて
最初の形はとどめていないけれど
もとの置いたままの形が好きだったけれど
僕が動かしたわけでもなく
君が動かしたわけでもなく
夢中に過ごした時間の中で
気がついたら 変っていた
君を残したまま
遠く生まれた場所を想い
今 生きていこうとしている場所を捜している
すぐに見つかるわけではないが
予感を胸に きっと生きている
朝が来る度 湧きあがる衝動
めくるめく 建物の群れ
胸騒ぎがして ビルの上に駆けあがる
雲一つない青空
息を切らしたまま
空を見上げた この瞬間!
この瞬間に生きている!
眼下の街――
君の柔らかい胸の音
港街
誰の事も知らない
誰も僕を知らない
この街にたどりついた
孤独好きの寂しがりや
音楽が流れてきそうだ
遠く観覧車も見える
奇妙なビルも視線の隅に 一人歩き出す
水道の蛇口が壊れている空き地
白く高いコンクリートの崖
どこに続くか分からない坂道を上って行くと 学校があった
休日なので人影もなく
金網に登り 足をぶらつかせ 街の全景を眺めてみる
校舎から吹いてくる風が なぜか冷たすぎる
この青い空が 昔見た空と違う色なのではないかと 一人首を傾げる
自分が落ちるより 空が落ちてきそうだ
街のあらゆる方向に走っている道路を目で追うと
全てが小さく 自分の視界に収まる風景に
今 この自分がいる世界とは違う世界で
何かが勝手に息衝き
何かが勝手に自分とは関係なく
通り過ぎていく
時々 遠くからクラクションの音が 小さく聞こえる
このまま目を閉じて 永遠の果てまでこうしていようか
とにかくここで暮らしていくのだ
わずかな夢を生活に変え 必死に暮らしていくのだ
この街の中で 君の想い出の中に
この消えかかる物語を いったい誰が憶えていようか!
月と舟
さまよう舟で 夜明けを待って
ただ 月を見ている
潮風に身をまかせ くるくると舟はまわる
暗闇の中 近くで腕を振る音が聞こえる
波間に落とした指輪 海の底から人魚よ
いつか僕に届けておくれ
今夜だけは 素直でいたい
月を美しいと想い 神秘の世界に驚き
水平線のおぼろげな光の中
目を閉じ 息を吸って 漂っていたい
ただそれだけでいい
さまよう舟で 夜明けを迎えて
子供の泣く声が聞こえる
シンフォニー
山の上から背伸びして まわりを眺めていると
おぉ 暗闇と光の狭間に 滑り込むのは音楽だ!
それはレンズみたいに歪みながら あたりを漂う
自分も音の波に乗って うねりながら漂う
緑の牧場(まきば)に 砂丘の向こうに
空と緑と湖の放つ 光の群れに 洪水に
高音と振動を起こしながら うなりをあげ突き進む
山にこだまするトレモロ
赤いトンガリ帽の妖精が踊りだす
ケルンの上で ホルンを持って
僕と世界を駆け巡る音楽の群れを
ふと 見失った時
背後から影が忍び寄る
口笛吹きながら忍び寄る
振り向くと 僕の口に人差し指をあて 黙らせる少女
左手を後ろに隠している
たぶん 花を一輪 持っている
彼女は口笛を吹いているのに
不思議と辺りは静寂に包まれているのだった
永遠
波がざわめき
夕陽が黄金色に海を染め
ローレライの唄が聞こえる
人魚のウロコを探す青年は 岩の上に立ち
遠く クジラの鳴き声を聞く
水夫のいない舟は 自然と入り江に集まり
一艘 行方知れずの舟は 潮の流れに身を任せる
もう 忘れ去られた満天の星空の中
その舟に二つの影が起き上がる
少年は星の物語を語り
少女は祈るように星を見つめる
月の光が雲の裂け目から差し込み
魚の群れに反射し
風が果実の豊潤な匂いを運び
舟がダンスを踊るようにただよう
時の経つのを忘れた少年の声が 聞こえなくなった時
月明かりが二人だけを照らし出す
すると 辺りを無数の魚が飛び跳ね
蝶の大群はいっせいに海上を渡り過ぎる
少女の瞳にその光景が映しだされると
少女は手をあわせたまま つぶやく
「まあ、まるで夢を見ているよう・・・・・・」
そも 永遠とは?
幻夢
空が不思議な紫色に染まり、にわかに湧き出した黒雲の裂け目から、太古の巨人が地上を覗きこみ、息を吹き掛ける。
地の果てから魔法使いが現れて、山の向こうを指し、
「見よ、災いが速やかにやって来る」と言って杖を鳴らす。
パルナシオンの山に天使は辿り着いただろうか?
地の裂け目を××天使が降りていく――底へ底へと。
魔法使いが両手を広げ天を仰ぐ。
巨人の息吹は嵐になり、地を這い、うなるように向かって来る。
竜巻が凄まじい勢いで人間を襲う。
風車は傾きながら回り続ける。
鳥は自由に飛ぶ事も出来ず、馬は狂ったように走り続ける。
狼は、「自然の災いは予測出来るが、魔物や人間のもたらす災いは予測出来ない」と片足を引きずりながら呟く。
空に向かって涙をこらえていた僕はというと、風に涙を吹き飛ばされただけ。
やがて、嵐の過ぎ去った後では、どこからともなく人々が現れ、残骸からとりあえず雨と風とをしのげるぐらいの小屋を作りだし、そこに集まって新しい家の設計を話し合う。
魔法使いは諦め、地の果てに消えて行き、巨人は雲の裂け目を閉じ、雷鳴と共に去って行く。
空に雲がなくなり、青空が広がると、ただ、太陽だけが、穏やかに地上を照らしているのだった。
恋歌
愛しい人は無邪気に笑い
僕はその横にいた
愛しい人と手をつなぐと
世界は変わって見えた
いや 僕ら二人が変わったのだ
愛しい人は色々な人に優しく
愛しい人は僕を時々忘れる
愛しい人のぬくもりは おぼろげで
僕も時々忘れてしまう
愛しい人は無邪気に笑って
僕はただ 穏やかでいる
愛しい人の瞳は僕と似ていて
愛しい人の気持ちは常にそこにある
僕はこの人が好きだ
クリスマス スノウ
霜焼けの君の手に 毛糸の手袋を渡して
列車は通り過ぎる
踏切りの向こうは 焚き火の煙でかすみ
こちらまで迫ってくる
目を細めると 煙が染みて 涙が落ちる
冬の線路を 君と渡ると
枯木の枝をふるう音や パンの焼く匂いなど
気になりながら ただ 歩く
悲しくもない僕の頬に 涙の跡を見つけて 君は笑う
その手は 口元近くにあって 白く息がはずむ
何一つ言うでもなく 何一つ聞くでもなく
自然と手をつないで 走り出す
氷の上を滑るように
息が切れてもかまわずに
やがて 君はふいに立ち止まり
空を見上げると
上気する君の額に 雪は静かに舞い降りる
パステル
彼女の白い頬と 口元に桃色のうぶ毛
息をするたび 揺れる黒髪
澄んだ香り 女の物腰
ピアノを弾く指が急ぎ出す
それは流線を描くのだが
ひじのあたりは直線的
もれる歌声は春風にのって 湖畔の緑を漂うよう
キラめく街々に繰り出す エネルギーは虹色に
明るく 世界を美しく照らし出す
靴音はクラシックに ブラウンの瞳は遠く
ビルの向こう 銀色の月を見つめている
夢見る世界への旅行
オレンジ色の列車に乗って行くのだそうだ
荷物をまとめて 旅立つ君の唇は
モンマルトルの紅い色
恋というものは
あなたへの想いも滞り
ようやく諦めようと思う
窓の外は寒く
ガラスに氷が張り付いているようで
時折ピシリッと音をたてる
その音がする度 我に返り
もう一度 思い直し
もう一度 やり直してみようと思うのだが
しかし 窓の外は寒く 冷たい音がする度に
私の想いも悲しみも
冷たく 深いところにあるのだと気づく
誰も解る筈もなく
誰も助けてくれず
誰も知らない間に
時間という長さのなかで 愛せなくなってしまい
私のこの悲しみは
深く 寒いところにあるのだと気づく
酔いどれ
また酒浸りの日々に戻ってしまった
酔いどれの日々
救われない魂が 今夜も街をさまよい歩く
けっして忘れた訳ではない
いつも新しい予感に目覚める
目覚めるが また よどんでしまう毎日に
昨日の夢は置き去りに
愛情は過ぎ去ったかのように思われる
重く苦しい足取りに
気が付くと 道端に転んでいて
泣いてみたりもする
恋歌の終わりに
恋歌の終わりに 煙草など吸って 空を見上げる
公園の中 ベンチに座り
落ちて来る花びらを 目で追いながら
深く また 吸い込む
遠い過去に泣き濡れた
煙のような魂は
もう ここにはいない
空高く昇り 消え去ってしまった
過去には激しく
今は落ち着いた気持ちが ここにある
片腕を背もたれに ここにいる
満開の桜が舞うのを見つめながら
もう いいじゃないかとここにいる
前半部終わり 後半部へ続く
トップページへ
Copyright(C)2000- Toshiaki Hirabayashi. All Rights Reserved.